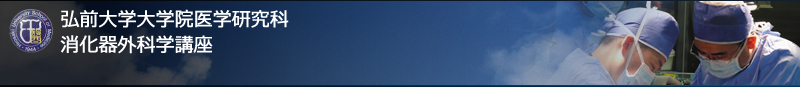
教室沿革・歴史
弘前大学第2外科学教室は昭和24年に槇哲夫先生(東北大学名誉教授、日本外科学会名誉会長、東北労災病院名誉院長)により開講されました。槇教授が昭和36年に東北大学へ転出されてからは2代目教授として大内清太先生が着任されました。この間昭和46年には上部消化管、下部消化管、肝胆膵、小児外科・乳腺・甲状腺の疾患別グループ制を導入され、これによって研究、教育、診察面の効率は著しく改善され、教室の業績も飛躍的に向上しました。
昭和56年4月からは小野慶一教授が3代目教授として昇任されました。小野教授は胆道の基礎科学的研究に関し、国際的評価を得ており、経十二指腸括約筋形成術、肝門部空腸吻合術等の胆道ドレナージ手術で有名であります。
平成3年3月からは今充教授が4代目教授として昇任されました。今教授は大腸癌、特に直腸癌における低位前方切除術の先駆者として、自律神経温存手術など患者のQOLを重視した治療に情熱を注がれました。また平成6年には青森県で初めての生体部分肝移植を指揮し、教室一丸となって成功させました。
平成9年4月からは佐々木睦男教授が5代目教授に昇任しました。佐々木教授は肝・胆・膵の基礎・臨床研究に従事し、肝内結石症の成因の解明とその治療法の確立や有茎間置空腸を用いた幽門輪温存膵頭十二指腸切除術で評価が高く、また国内で早期から生体部分肝移植のイヌを用いた研究に着手し、イヌで国内最長生存記録を樹立しました。その経験を臨床に生かし、平成6年から教室における生体部分肝移植を執刀しています。
平成20年8月からは袴田健一教授が6代目教授に昇任されました。袴田教授は、前任の佐々木教授とともに教室における生体部分肝移植の基礎研究から臨床応用まで、初期の段階から関わり良好な治療成績を上げております。最近ではその研究を、肝再生機構の遺伝子解析・人工肝開発へと発展させております。また、肝臓癌手術・膵臓癌手術の治療成績の治療成績の向上を目指し、新しい手術手技の開発・画像診断の開発を行っております。
以上のように教室創立以来現在まで一貫して消化器外科の診療、研究、教育に力を注いで来ました。
特に生体部分肝移植、大腸・肛門病の分野では全国をリードしております。したがって本邦における当教室の一般外科ならびに消化器外科としての評価は高く、現在まで全国規模の学会としては第13回(昭和46年)および第27回(昭和60年)日本平滑筋学会、第12回(昭和53年)および第28回(昭和61年)日本消化器外科学会総会、第34回(昭和54年)および第51回(平成8年)日本大腸肛門病学会、第9回(昭和61年)膵管胆道合流異常研究会、第23回(昭和62年)日本胆道学会、第7回(平成8年)日本性機能学会第16回(平成11年)日本胆膵生理機能研究会と多数にわたって主催しております。開講以来60年、この間にはぐくまれた同門生は350余名を数えております。同門会は三葉会と称し、先輩各位は全国各地で活躍しており教室の発展と我々後輩の教育を支える多大な力になっております。
教室からはこれまでに第2外科教室以外にも、津嶋恵輔教授(弘前大学医療短期大学:昭和50年4月〜昭和59年9月)、杉山譲教授(弘前大学医療短期大学:昭和59年4月〜平成11年4月)、棟方博文教授 (弘前大学医学部小児外科:平成9年12月〜現在)、羽田隆吉教授(弘前大学医学部医療情報部:平成8年12月〜現在)、伊東恭悟教授(久留米大学免疫学:平成4年6月〜現在)を輩出しており、臨床のみならず基礎的分野においても全国的に活躍しております。
現教室員の留学経験者
国外
- 小田桐弘毅
- 講師 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
- 鳴海 俊治
- 講師 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
- 川崎 仁司
- 講師 ハーバード大学
- 豊木 嘉一
- 助教 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
国内
- 小田桐弘毅
- 講師 癌研附属病院
- 川崎 仁司
- 講師 国立ガンセンター
- 宮本 慶一
- 助教 国立ガンセンター
- 坂本 義之
- 医員 東北大学加齢医学研究所
海外からは昭和63年度には上海第2医科大学より呉志勇君が半年、またイタリアよりフランシスコ・マロッタ君が文部省国費留学生として1年間在局し、この間実験的急性膵炎について研究を行い、平成2年本学で医学博士の学位を授与されています。平成2年にはブラジルより土佐・ミルトン・差登司君が同じく文部省国費留学生として2年間在局、平成4年には中国より呉碩東君が、最近では平成8年10月から平成10年3月まではチリよりセバスチャン・ウリベ君が文部省国費留学生として在局しておりました。また、一般臨床医としての研修を行う派遣市中病院も多く、青森県、秋田、山形、北海道に出張研修しております。当教室より多数の院長を輩出していることも、我々後輩にとって、何よりも力強い礎であります。