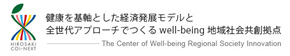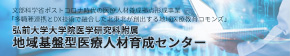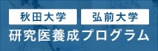- Home
- 学部・大学院について
- 特徴
特徴
特徴についての流れ
Ⅰ.医学研究科及び医学部附属病院の充実が進んでいます
平成19年度からの部局化に伴って、従来の講座・部門等はすべて大学院講座となり、一部は名称も変更になりました。また、平成19年度から腫瘍内科学講座が新設されるなど、教育研究組織の見直しが進んでいます。さらに、平成20年度には、サンスター株式会社からの寄附講座として、糖鎖医学講座が新設されました。平成21年度からは、研究科定員が50名になりましたが、弘前大学医学研究科は改革と充実が進み、その評価は大いに高まっています。Ⅱ.附属脳神経血管病態研究施設や各センターの研究が発展しています
平成11年に改組された「附属脳神経血管病態研究施設(脳研)」の存続が決定されました。同施設の組織は従前通りですが、脳神経科学を専門とする他のグループとも密接に連携してこの領域の研究がますます発展しています。このような附属の研究施設は、東北・北海道地区で唯一のものであり、脳神経科学研究は今後も本学における研究の柱の一つとして推進されていくものと考えられます。平成21年度には、「心の遺伝子リポジトリ形成」というタイトルの下に、脳神経科学研究に対する大型の特別研究経費が概算要求で認められました。これを契機に、より一層の研究の発展が期待されます。また、平成17年度に設置された高度先進医学研究センターには、分子生体防御学講座に、糖鎖工学講座、糖鎖医学講座(寄附講座)が加わり、本学独自の先進的研究が推進されています。
平成18年度から各研究科・学部の特別教育研究センターとして医学研究科に設置された"がん診療研究センター"、"移植医療研究センター"、"循環器病研究センター"、"健康・スポーツ医科学センター"においても、それぞれのテーマの下に、講座等の枠を越えて教育・研究能力を結集し、実績を挙げています。
Ⅲ.施設整備が進んでいます
平成20年度内に3年間にわたる総合研究棟(基礎研究棟)の改修が終了し、現在は、総合研究棟(臨床研究棟)の改修が2年計画で進んでいます。研究棟の改修は平成21年度をもって終了の予定であり、工事中は不便を余儀なくされてはいますが、終了後には、教育・研究のさらなる活性化を目指した環境が整備されます。Ⅳ.附属病院が発展しています
附属病院の施設整備が進んでいます
外来診療棟の新築工事が終わりました。臨床研究棟の改修が終了すると、医学部キャンパスの環境整備が始まります。これによって、駐車スペースの確保はもとより、キャンパス全体が一新されるものと期待されます。
高度救命救急センターが設置されます
平成22年度には、附属病院に高度救命救急センターが新設されます。この高度救命救急センターは、我が国ではじめての緊急被ばく医療に対応した救命救急センターであり、我が国のエネルギー政策を支える重要な機能を果たすとともに、医学部附属病院が地域の救急医療の最後の砦としての役割を果たすために一層大きな力となるものです。また、同センターは、救急医療をはじめとする地域医療の担い手を育成するためにも、重要な機能を果たすものと期待しています。
附属病院の診療体制がますます充実しています
附属病院は青森県内唯一の特定機能病院であり、これまでに開発・承認された高度医療は①レーザー血管形成術、②血管内視鏡検査、③生体部分肝移植、④血管内超音波診断法、⑤皮膚色素異常症ルビーレーザー療法、⑥歯周組織再生誘導法、⑦インプラント義歯、⑧栄養障害型表皮水泡症のDNA診断の8種に達しています(このうち②~⑤は、その後、保険適用となったため、現在は①、⑥、⑧の3種)。
平成19年度に腫瘍内科が設置されたことや、高度救命救急センターの設置が平成22年度に予定されているなど、附属病院の診療体制の充実が確実に進んでいます。
附属病院の診療に貢献した教職員を表彰しています
附属病院の診療水準の向上に寄与した教職員を表彰しています。患者サービスの観点から、看護や事務関係の職員に「心のふれあい賞」、診療技術の向上に貢献した教職員に「診療技術賞」が授与されています。
| 弘前大学医学部附属病院診療奨励賞 | 代表 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 第一回 | 第二内科循環器救急診療システム | 藤野 安弘 | 内科学第二講座 |
| 全静脈麻酔とくにDFK法,PFK法の開発とその臨床応用 | 坂井 哲博 | 麻酔科 | |
| 放射線部内を生け花で装飾し患者サービスにつとめた | 山田 操 | 放射線部 | |
| 第二回 | 複数科協力体制による口腔,咽頭,喉頭,食道悪性腫瘍に対する遊離腸管移植手術の推進 | 小林 慎 | 外科学第一講座 |
| 新しい看護領域である継続看護のシステム構築 | 大和田優子 | 看護部 | |
| 『看護の日』メッセージカードを通しての患者様とのふれあい | 阿部よし子 | 看護部 | |
| 第三回 | 医薬品臨床試験(治験)時における治験コーディネーター(CRC)の貢献 | 工藤 正純 | 治験管理センター |
| 患者用図書館開設に係るボランティア活動(病院ボランティア活動を通しての患者とのふれあい) | 谷山理阿子 | 病院ボランティア | |
| 第四回 | 検査結果迅速報告のための早出勤務体制の構築 | 斉藤 順子 | 検査部 |
| 放射線部における新放射線部情報システムの構築 | 尾崎 博一 | 放射線部 | |
| 心温まるお祝い食の導入 | 平野 聖治 | 医事課栄養管理室 | |
| 第五回 | 小児悪性固形腫瘍の集学的治療体制の構築 | 照井 君典 | 小児科 |
| 当科における術後在宅化学療法の意義-末期癌患者のQOL向上を目指して- | 村田 暁彦 | 第二外科 | |
| 第六回 | 国立大学病院薬剤部としてのISO9001:2000の認証取得 | 藤田 祥子 | 薬剤部 |
| 内視鏡をもちいた伝音難聴の新しい診断法と手術法の開発-経鼓膜的内視鏡下鼓室形成術- | 欠畑 誠治 | 耳鼻咽喉科 | |
| 第七回 | 形成不全に伴う変形性股関節症に対する弘前大学式セメントレス大腿骨ステムの開発と臨床応用 | 中村 吉秀 | 整形外科 |
| 膀胱全摘除術後のQOLを向上させる新規回腸新膀胱「弘前膀胱」の考案 | 古家 琢也 | 泌尿器科 | |
| 院内スタッフ間の協力体制による社会的自立へ向けた患者支援 | 三浦 恒子 | 看護部 | |
| 第八回 | 弘前大学式低侵襲前立腺全摘除術の術式と教育システムの確立 | 古家 琢也 | 泌尿器科 |
| 急性大動脈解離に対する緊急対応-特に脳分離体外循環を必要とする緊急手術の対応- | 佐藤 正治 | 臨床テクノロジーセンター | |
| 病院の諸行事に貢献している | 船水 亮平 | 医療情報部 | |
| 第九回 | 体外受精・胚移植法における4日目桑実胚移植 | 木村 秀崇 | 産科婦人科 |
| 診療科の枠組みを超えた『腎移植ユニット』の構築 | 米山 高弘 | 泌尿器科 | |
| 看護部感染対策委員会リンクナースの活動 標準予防策の遵守率向上への貢献 | 山本 葉子 | 看護部 | |
| 第十回 | 投球障害肩・野球肘に対する投球フォーム指導による治療 | 塚本 利昭 | リハビリテーション部 |
| 携帯型超音波画像診断装置を用いた末梢神経ブロックへの応用技術-ランドマーク法から視覚的穿刺法へ- | 北山 眞任 | 麻酔科 | |
| 精神疾患患者に対する園芸作業と院内美化 | 相馬美香子 | 看護部 | |
| 第十一回 | がん医療専門職協働による外来化学療法の質的,量的向上 | 佐藤 淳 | 腫瘍センター |
| 集中治療室におけるブドウ糖希釈法による重症患者の体液量評価 | 橋場 英二 | 集中治療部,麻酔科,手術部,救急・災害医学講座 | |
| 静脈血栓塞栓症の予防と治療のとりくみ | 谷口 哲 | 呼吸器外科・心臓血管外科,放射線科 | |
| 第十二回 | 術創トラブルを解消する皮膚縫合法の工夫 | 古家 琢也 | 泌尿器科 |
| 液状細胞診(Liquid Base Cytolory)の導入による「がん細胞」診断精度の向上 | 刀稱 亀代志 | 病理部 | |
| 新外来棟における季節感を演出した患者サービス | 岡崎 耕衛 | 医事課 | |
| 第十三回 | ベッドサイド細胞診導入による細胞診断の精度向上と患者負担の軽減 | 刀稱 亀代志 | 病理部 |
| 臨床応用を目的とした「てんかん責任遺伝子診断用DNAチップ」 | 菊地 隆 | 神経精神医学講座 | |
もの忘れ外来および認知症ネットワークの確立 |
瓦林 毅 | 神経内科 | |
| 集中治療部における呼吸器管理へ経食道エコー法の導入と応用 | 橋場 英二 | 集中治療部 | |
| 第十四回 | ベッドサイド細胞診導入による細胞診断の精度向上と患者負担の軽減 | 刀稱 亀代志 | 病理部 |
| 臨床応用を目的とした「てんかん責任遺伝子診断用DNAチップ」 | 菊地 隆 | 神経精神医学講座 | |
| 小児科病棟における成長・発達を促す遊びの場の提供 | 松田 和子 | 看護部 | |
| 第十五回 | 超音波診断装置画像配信システムの構築 | 小島 桂也 | 検査部 |
| 下部直腸癌患者に対する究極の肛門温存術式"内括約筋切除術"の貢献 | 村田 暁彦 | 消化器外科,乳腺外科,甲状腺外科 | |
| ストーマ・ケアから伝わるふれあいと情愛 | 鎌田 恵理子 | ||
| 第十六回 | 心電図モニター適正運用へ向けた取り組み:モニターアラームの現状とその対策 | 富田 泰史 | 循環呼吸腎臓内科学講座 |
| 固定用テープの手書きのイラストから伝わるやさしさ と思いやり | 石川 千鶴子 | 看護部 | |
Ⅴ.研究の中核である大学院がさらに充実しています
大学院の改革が進んでいます
平成19年度から、それ以前の大学院医学系研究科医科学専攻(博士課程)は、大学院医学研究科(博士課程)に変わりました。これは、以前の大学院医学系研究科保健学専攻に博士課程が新設されるに伴って、医学研究科と保健学研究科がそれぞれ独立することになったためです。これに際して、募集定員64名のうち9名が保健学研究科に振り替えられ、医学研究科の定員は55名になり、また、平成21年度からは更に5名減らして50名となりました。適正な定員の下で、教育研究のより一層の充実を果たすことが目的です。
既に医学系研究科医科学専攻の時代から、組織の見直しが実施され、大学院生は、各プロジェクトに対応する教育研究科目を修得し教育研究指導を受けるとともに、関連する他の教育研究科目を選択して、幅広い知識・技術を習得できます。
大学院教育課程の実質化
大学院教育の実質化は当然ですが、既に医学系研究科医科学専攻の時代から、医学・生命科学研究の基本的理論と技術を身に付けるための共通科目及び学際科目を設定し、定期的な講義を実施してきました。これを基本として、見直しを続けるとともに、各講座においても、それぞれの講義・演習等を設定し実施しています。
遠隔地勤務の社会人入学者に対する大学院講義
平成11年度から、社会人入学者を対象に双方向テレビ会議システムを用いた、遠隔地の病院等と弘前大学とを結ぶ双方向通信による大学院講義を実施しています。現在ではおよそ20箇所の病院等と結んで講義が実施されています。また、社会人大学院生への配慮の一環として、一部では集中講義などの工夫も行われており、遠隔地の社会人大学院生にも適切な教育研究の機会が整備されています。
学位論文の英文校正
平成9年度から、メディカル・イングリッシュ・センターを設置し、英語論文の校正を行っています。最近の学位論文のほぼすべては英文で、その大部分が国際誌に公表されていますが、同センターの役割も大変大きなものがあります。
修業年限短縮制度
3年または3年半以内に必要な単位を取得し、優れた学位論文がまとまれば、早期に大学院を修了し博士(医学)の学位を取得することができます。平成13年度1名、平成15年度1名、平成17年度2名、平成18年度1名、平成19年度4名、平成20年度2名が、本制度により3年または3年半で修了しています。
Ⅵ.医学研究科の研究実施体制が強化されています
外部研究資金によるプロジェクトの推進
医学研究科・医学科では、「唐牛記念医学研究基金」による研究支援を長年実施してきました。平成20年度の第27回唐牛記念医学研究基金助成は、助成金Aが「癌の高悪性度形質を制御する時計遺伝子の機能解析」(病理生命科学講座 鬼島 宏 教授)と「光線力学的療法と新規抗腫瘍剤を併用した卵巣癌治療法の開発」(産科婦人科学講座 横山良仁 講師)に、助成金Bが「Nrf2が活性化する自然免疫系の解明」(分子生体防御学講座 丸山敦史 助教)に決定されました。
平成16年度からの都市エリア産学官連携促進事業による「プロテオグリカン応用研究プロジェクト」(糖鎖工学講座等)は、平成19年度から更に3年間の延長が認められ、また、平成21年度には、脳神経科学研究グループによる「心の遺伝子レポジトリ形成」が特別教育研究経費として採択されました。
これからも、基礎・臨床融合型研究プロジェクトを立ち上げ、学内外の資源による集中的支援を実施していくこととしています。
弘前大学医学部学術賞
(1)学術特別賞
本学における多くの研究の中から特に優れた研究を毎年選んで、学術特別賞を授与しています。これまでの受賞者は以下のとおりで、この中の5人は本学の教授に、また、他の5名は他大学の教授に就任しています。
| 弘前大学医学部学術特別賞 | 受賞者 | 職名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 平成8年度 | 伊藤 悦朗 | 講 師 | 附属病院小児科 |
| 宇佐美真一 | 助教授 | 耳鼻咽喉科学講座 | ||
| 第二回 | 平成9年度 | 高垣 啓一 | 助教授 | 生化学第一講座 |
| 渡部 肇 | 講 師 | 附属病院第三内科 | ||
| 第三回 | 平成10年度 | 澤村 大輔 | 講 師 | 皮膚科学講座 |
| 廣田 和美 | 助 手 | 附属病院麻酔科 | ||
| 第四回 | 平成11年度 | 岡田 元宏 | 助 手 | 神経精神医学講座 |
| 第五回 | 平成12年度 | 菅野 隆浩 | 助教授 | 生理学第一講座 |
| 大熊 洋揮 | 講 師 | 脳神経外科学講座 | ||
| 第六回 | 平成13年度 | 土岐 力 | 助 手 | 小児科学講座 |
| 第七回 | 平成14年度 | 小谷 直樹 | 講 師 | 附属病院麻酔科 |
| 第八回 | 平成15年度 | 森 文秋 | 助教授 | 脳神経血管病態研究施設分子病態部門 |
| 第九回 | 平成16年度 | 今泉 忠淳 | 助 手 | 脳神経血管病態研究施設脳血管病態部門 |
| 大黒 浩 | 助教授 | 眼科学講座 | ||
| 第十回 | 平成17年度 | 古郡 規雄 | 講 師 | 神経精神医学講座 |
| 蔭山 和則 | 講 師 | 附属病院内分泌感染症代謝内科 | ||
| 第十一回 | 平成18年度 | 今 淳 | 助教授 | 生化学第一講座 |
| 第十二回 | 平成19年度 | 胡 東良 | 准教授 | 感染生体防御学講座 |
| 第十三回 | 平成20年度 | 柿崎 育子 | 准教授 | 糖鎖工学講座 |
| 横山 良仁 | 講 師 | 産科婦人科学講座 | ||
| 第十四回 | 平成21年度 | 杉本 一博 | 准教授 | 臨床検査医学講座 |
| 中野 創 | 准教授 | 皮膚科学講座 | ||
| 第十五回 | 平成22年度 | 下山 克 | 講 師 | 附属病院消化器内科 |
| 皆川 正仁 | 講 師 | 胸部心臓血管外科学講座 | ||
| 第十六回 | 平成23年度 | 浅野 研一郎 | 講 師 | 脳神経外科学講座 |
| 丹治 邦和 | 助 教 | 脳神経病理学講座 | ||
| 第十七回 | 平成24年度 | 櫛方 哲也 | 麻酔科 | |
| 松宮 朋穂 | 脳血管病態学講座 | |||
| 第十八回 | 平成25年度 | 水上 浩哉 | 講師 | 分子病態病理学講座 |
| 菅原 典夫 | 講師 | 神経科精神科座 | ||
| 第十九回 | 平成26年度 | 嶋村 則人 | 講 師 | 脳神経外科学講座 |
| 福井 淳史 | 講 師 | 産科婦人科 | ||
| 第二十回 | 平成27年度 | 富田 泰史 | 准教授 | 循環器腎臓内科学 |
| 第二十一回 | 平成28年度 | 樋熊 拓未 | 准教授 | 心臓血管病先進治療学講座 |
| 古家 琢也 | 准教授 | 泌尿器科学講座 | ||
| 第二十二回 | 平成29年度 | 木村 正臣 | 准教授 | 高血圧・脳卒中内科学講座 |
| 第二十三回 | 平成30年度 | 櫻庭 裕丈 | 准教授 | 消化器血液内科学講座 |
| 第二十四回 | 令和元年度 | 珍田 大輔 | 講 師 | 地域医療学講座 |
| 第二十五回 | 令和2年度 | 西嶌 春生 | 助 教 | 脳神経内科 |
| 第二十六回 | 令和3年度 | 藤田 敏次 | 准教授 | ゲノム生化学講座 |
| 畠山 真吾 | 准教授 | 先進血液浄化療法学講座 | ||
(2)学術奨励賞
毎年、2年前以降に学術雑誌に発表された論文の中から特に優れたものを選んで、学術奨励賞を授与しています。受賞者は以下のとおりですが、年ごとに受賞論文のレベルが高くなっており、医学研究科全体の研究レベルの向上を反映しています。
| 弘前大学医学部学術奨励賞 | 受賞者 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 第一回 | 平成8年度 | 一戸 紀孝 | 解剖学第一講座 |
| 坂本 十一 | 附属病院第一内科 | ||
| 第二回 | 平成9年度 | 神村 典孝 | 生理学第一・泌尿器科学講座 |
| 安井 規雄 | 神経精神医学講座 | ||
| 第三回 | 平成10年度 | 孟 民 | 皮膚科学講座 |
| 小山 基 | 病理学第一講座 | ||
| 第四回 | 平成11年度 | 馬場 貴子 | 皮膚科学講座 |
| 田澤 俊幸 | 外科学第二講座 | ||
| 第五回 | 平成12年度 | 佐々木真吾 | 附属病院第二内科 |
| 高橋 克郎 | 外科学第二講座 | ||
| 第六回 | 平成13年度 | 水木 大介 | 細菌学講座 |
| 中野 高広 | 脳神経外科学講座 | ||
| 第七回 | 平成14年度 | 奈良 昌樹 | 外科学第二講座 |
| 石戸圭之輔 | 生化学第一講座 | ||
| 第八回 | 平成15年度 | 差波 拓志 | 細菌学講座 |
| 中野あおい | 国立弘前病院皮膚科 | ||
| 第九回 | 平成16年度 | 木村 正臣 | 三沢市立三沢病院第三内科 |
| 神尾 卓哉 | 大館市立総合病院小児科 | ||
| 第十回 | 平成17年度 | 池島 進 | 青森県立中央病院内分泌内科 |
| 富田 泰史 | 弘前脳卒中センター内科 | ||
| 第十一回 | 平成18年度 | 七嶋 直樹 | 医学部保健学科 |
| 工藤 貴徳 | 附属病院内分泌・糖尿病代謝内科・感染症科 | ||
| 第十二回 | 平成19年度 | 櫻庭 裕丈 | 消化器内科・血液内科・膠原病内科 |
| 第十三回 | 平成20年度 | 神 可代 | 皮膚科学講座 |
| 佐藤 知彦 | 西北中央病院小児科 | ||
| 第十四回 | 平成21年度 | 山田 雅大 | 病態薬理学講座 |
| 佐藤 裕紀 | 三沢市立三沢病院 | ||
| 棟方 聡 | 附属病院脳神経外科 | ||
| 第十五回 | 平成22年度 | 今野 友貴 | 附属病院小児科 |
| 太田 健 | 国立病院機構弘前病院消化器血液内科 | ||
| 第十六回 | 平成23年度 | 三浦 卓也 | 青森市民病院 |
| 鈴木 一広 | 三沢市立三沢病院 | ||
| 第十七回 | 平成24年度 | 澁谷 修司 | 大館市立総合病院 |
| 小田桐 沙織 | 神経解剖・細胞組織学講座 | ||
| 高橋 一徳 | 青森県立中央病院 | ||
| 第十八回 | 平成25年度 | 田中 寿志 | 循環器内科,呼吸器内科,腎臓内科 医員 |
| 第十九回 | 平成26年度 | 鎌田 耕輔 | 大館市立総合病院 |
| 松田 尚也 | 脳神経外科学講座 | ||
| 第二十回 | 平成27年度 | 三木 康生 | 脳神経病理学講座 |
| 村澤 真吾 | 内分泌代謝内科学講座 | ||
| 第二十一回 | 平成28年度 | 王 汝南 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 金城 貴彦 | むつ総合病院 | ||
| 第二十二回 | 平成29年度 | 安 欣 | 中国医科大学付属第一医院 |
| 奈良岡 征都 | 附属病院脳神経外科 | ||
| 第二十三回 | 平成30年度 | 齋藤 傑 | 国際医療福祉大学病院 |
| 飯野 勢 | 附属病院消化器内科・血液内科・膠原病内科 | ||
| 第二十四回 | 令和元年度 | 市川 博章 | 青森市民病院 |
| 追切 裕江 | 国立病院機構弘前病院 | ||
| 第二十五回 | 令和2年度 | 郭 丹陽 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 横野 良和 | むつ総合病院 | ||
| 第二十六回 | 令和3年度 | 高橋 和久 | 八戸市立市民病院 |
Ⅶ.学部教育が絶えず改善されています
弘前大学医学部医学科の授業カリキュラム
平成13年に作成されたコア・カリキュラムが導入されて以降、平成20年度の改訂に伴って、地域医療関連教育、研究マインドを育てる教育などが導入されましたが、本学医学部医学科においては、平成18年度から地域医療実習を,平成16年度から研究室研修を実施してきました。 カリキュラムに関しては、平成18年度からカリキュラムWGを組織し、絶えず検証と見直しを行う体制を整備するとともに、平成21年度からは、地域医療教育の強化を中心とした新しいカリキュラムによる学部教育を開始しています。
医学科学生定員増
医学科学生定員は、平成20年度に10名、平成21年度には更に10名の増員が認められ、現在は過去最大定員の120人となりました。これに伴い、教育設備等の充実を進めてきましたが、加えて医学部医学科、医学部附属病院は総力を挙げて、学部教育に取組んでいます。
社団法人青森医学振興会による支援
平成11年3月に医学部医学科後援会としてスタートした「鵬桜医学振興会」を母体として、平成13年4月から「社団法人青森医学振興会」が設立されました。教職員、学生保護者、医学部医学科同窓会会員、医療機関などからの寄附を募り、学生教育に関連した設備、行事のための支援が行われています。一例として、実習室の環境整備、学生課外活動援助、学生表彰などが青森医学振興会によって支援されており、同振興会は医学科の教育活動を強力に支えています。
熱心な教員に国際化教育奨励賞を授与し、海外の医学教育の視察に派遣しています
学部・大学院教育に熱心な教員を学務委員会が国際交流研究委員会に推薦し、国際交流の一環として、毎年数名の教員を海外の教育事情の視察に派遣しています。これまでの受賞者は以下の通りです。
| 国際化教育奨励賞 | 受賞者 | 職名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 平成 9年度 | 植山 和正 | 講 師 | 附属病院整形外科 |
| 高橋 敏 | 助 手 | 附属病院集中治療部 | ||
| 高橋 敏夫 | 講 師 | 附属病院脳神経外科 | ||
| 吉田 秀見 | 講 師 | 脳研病態生理部門 | ||
| 泉井 亮 | 教 授 | 生理学第一講座 | ||
| 第二回 | 平成10年度 | 尾金 一民 | 助 手 | 附属病院脳神経外科 |
| 高橋 元 | 助教授 | 解剖学第二講座 | ||
| 竹内 功 | 助 手 | 外科学第一講座 | ||
| 佐々木甚一 | 講 師 | 細菌学講座 | ||
| 八木橋操六 | 教 授 | 病理学第一講座 | ||
| 第三回 | 平成11年度 | 正村 和彦 | 教 授 | 解剖学第一講座 |
| 吉村 教 | 助教授 | 病理学第二講座 | ||
| 坂井 哲博 | 講 師 | 附属病院麻酔科 | ||
| 奥村 謙 | 教 授 | 内科学第二講座 | ||
| 新川 秀一 | 教 授 | 耳鼻咽喉科学講座 | ||
| 第四回 | 平成12年度 | 菅野 隆浩 | 助教授 | 生理学第一講座 |
| 兼子 直 | 教 授 | 神経精神医学講座 | ||
| 石橋 恭之 | 助 手 | 整形外科学講座 | ||
| 工藤 誠治 | 講 師 | 泌尿器科学講座 | ||
| 廣田 和美 | 助 手 | 附属病院麻酔科 | ||
| 第五回 | 平成13年度 | 高橋 信好 | 助教授 | 泌尿器科学講座 |
| 小林 恒 | 助教授 | 歯科口腔外科学講座 | ||
| 馬場 正之 | 助教授 | 脳研神経統御部門 | ||
| 浅野研一郎 | 助 手 | 附属病院脳神経外科 | ||
| 第六回 | 平成14年度 | 嶋村 則人 | 助 手 | 脳神経外科学講座 |
| 第七回 | 平成15年度 | 橋場 英二 | 医 員 | 附属病院麻酔科 |
| 中村 吉秀 | 助 手 | 整形外科学講座 | ||
| 第八回 | 平成16年度 | 花田 裕之 | 講 師 | 内科学第二講座 |
| 庄司 優 | 助教授 | 臨床検査医学講座 | ||
| 第九回 | 平成17年度 | 福田 幾夫 | 教 授 | 外科学第一講座 |
| 第十回 | 平成18年度 | 鈴木 保之 | 助教授 | 外科学第一講座 |
| 遠瀬 龍二 | 医 員 | 附属病院麻酔科 | ||
| 第十一回 | 平成19年度 | 丹羽 英智 | 医 員 | 附属病院麻酔科 |
| 皆川 正仁 | 講 師 | 胸部心臓血管外科学講座 | ||
| 第十二回 | 平成20年度 | 下山 克 | 講 師 | 附属病院消化器内科・血液内科・膠原病内科 |
| 大徳 和之 | 講 師 | 胸部心臓血管外科学講座 | ||
| 第十三回 | 平成21年度 | 中村 典雄 | 講 師 | 附属病院循環器・呼吸器・腎臓内科 |
| 福井 淳史 | 助 教 | 附属病院産科婦人科 | ||
| 第十四回 | 平成22年度 | 袴田 健一 | 教 授 | 消化器外科学講座 |
| 福井 康三 | 准教授 | 附属病院医療安全推進室 | ||
| 第十五回 | 平成23年度 | 石戸 圭之輔 | 消化器外科学講座 | |
| 工藤 隆司 | 麻酔科 | |||
| 第十六回 | 平成24年度 | 谷口 哲輔 | 助教 | 胸部心臓血管外科学講座 |
| 森本 武史 | 助教 | 循環呼吸腎臓内科学講座 | ||
| 第十七回 | 平成25年度 | 福田 和歌子 | 助教 | 胸部心臓血管外科学講座 |
| 第十八回 | 平成26年度 | 豊木 嘉一 | 准教授 | 医学研究科消化器外科学講座 |
| 工藤 倫之 | 助教 | 医学部附属病院麻酔科 | ||
| 第十九回 | 平成27年度 | 上里 涼子 | 助教 | 医学部附属病院整形外科 |
| 第二十回 | 平成28年度 | 木村 大輔 | 助教 | 医学研究科胸部心臓外科学講座 |
| 第二一回 | 平成29年度 | 吉澤 忠司 | 助教 | 医学研究科病理生命科学講座 |
| 櫻庭 裕丈 | 講師 | 医学研究科地域医療学講座 | ||
| 第二二回 | 平成30年度 | 富田 泰史 | 教授 | 医学研究科循環器腎臓内科学講座 |
| 水上 浩哉 | 教授 | 医学研究科分子病態病理学講座 | ||
| 第二三回 | 令和元年度 | 花田 裕之 | 教授 | 医学研究科救急・災害医学講座 |
| 浅野 クリスナ | 教授 | 医学研究科感染生体防御学講座 | ||
Ⅷ.弘前大学医学部医学科の入試改革
平成18年度入試から導入された推薦入試の青森県枠15名を、平成19年度は20名、20年度は30名に増やしてきました。特に平成20年度は臨時学生定員増に伴って、従来から実施していた推薦入試地域枠を増やすにとどめましたが、平成21年度からは、更に10名の定員増に伴って、推薦入試を廃止して新たにAO入試(定員40名)を導入しました。これは、青森県の他に、北海道南部、秋田・岩手両県北部を含めた指定地域の高等学校出身者で、卒業後は弘前大学とその関連施設で勤務することを確約できる者を対象としています。選抜は、自己推薦書の他に面接や自学自習レポートを課し、センター試験の受験も義務付けています。また、平成15年度から定員20名で実施してきた3年次学士編入のうち、平成20年度から5名を青森県指定枠とし、青森県の高等学校または大学を卒業した者を対象として選抜を行っています。
さらに、平成21年度から認められた10名の定員増に伴って、一般入試(前期日程)募集定員を、それまでの50名から60名に増やし、そのうち10名は、出身地域を限定することなく、将来は弘前大学とその関連施設での勤務を義務付ける"地域指定枠"としました。
Ⅸ.国際交流事業
大学間交流
平成17年に中国医科大学と学部間の協定を締結しましたが、同大学からは毎年1名大学院生を基礎系講座に受け入れており、医学研究科の措置として3年間の就学支援を実施しています。
学部学生に関しては、アメリカ合衆国テネシー大学医学部との学部間協定に基づく学生派遣と、三沢米軍病院でのエクスターン実習が毎年行われており、いずれも数名の学生が派遣されています。
弘前国際医学フォーラム
弘前大学医学研究科では、平成9年から"弘前国際医学フォーラム"と銘打った国際シンポジウムを開催してきました。これは、先進的研究を行っている本学の研究グループが計画・運営する研究集会で、国内外の著名な研究者を招いて共に討議するものです。このフォーラムは平成19年の第11回まで毎年継続して開催されてきましたが、第12回は平成21年度に開催されました。
現在では、このシンポジウムのプロシーディングを「弘前医学」補冊として出版しており、先進的研究情報の世界発信の機会ともなっています。
| 実行委員長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成9年 | 第一回 | 細胞生物学 | 第一病理学 | 八木橋操六 | 教授 |
| 平成10年 | 第二回 | 分子医学 | 皮膚科学 | 橋本 功 | 教授 |
| 平成11年 | 第三回 | 臓器移植 | 第二外科学 | 佐々木睦男 | 教授 |
| 平成12年 | 第四回 | 糖鎖医学 | 第一生化学 | 遠藤 正彦 | 教授 |
| 平成13年 | 第五回 | 薬理遺伝学 | 神経精神医学 | 兼子 直 | 教授 |
| 平成14年 | 第六回 | 脳研究の進歩 | 脳血管病態部門 | 佐藤 敬 | 教授 |
| 平成15年 | 第七回 | 地域医療における国際協力 | 公衆衛生学 | 三田 禮造 | 教授 |
| 平成16年 | 第八回 | What's New in Organ Transplantation? | 整形外科学 | 藤 哲 | 教授 |
| 平成17年 | 第九回 | がん予防と治療の新たな標的 | 第二生化学 | 土田 成紀 | 教授 |
| 平成18年 | 第十回 | 生体防御の新しい概念 | 感染生体防御学 | 中根 明夫 | 教授 |
| 平成21年 | 第十一回 | Emerging Frontiers in Brain Research - Crossroads of metabolic regulation, stress response and disease- | 分子生体防御学 | 伊東 健 | 教授 |
| 平成22年 | 第十二回 | Sleep-wakefulness and feeding behavior -From genes to behavior- | 脳神経生理学 | 上野 伸哉 | 教授 |
| 平成23年 | 第十三回 | Innovation in Transplant and Regenerative Medicine | |||