血液グループ
臨床
弘前大学小児科血液グループでは、血液疾患、小児がん、免疫不全症を中心に診療を行っています。
小児がんは比較的まれな疾患であるため、正確な診断、適切な治療、より良い治療の開発を行うには、多くの施設が協力し合うことが重要です。当グループでは、それぞれの分野の全国規模の治療研究グループに所属し、診療にあたっています。白血病、悪性リンパ腫などの血液がんの分野では、小児白血病研究会(JACLS)と日本小児がん研究グループ(JCCG)に所属しており、細胞表面マーカー検査、遺伝子検査、病理検査などの検査については、それぞれの分野の専門家が担当するJCCGの中央診断を受けることができます。治療については、JCCGのそれぞれの疾患の治療研究委員会がより良い治療の開発のために作成した治療研究に参加することができます。該当する治療研究がない場合、あるいは該当する治療研究はあっても参加を希望されない場合には、現時点で最も良いと考えられる治療法を選択します。
当グループは、JCCGの中央診断施設の役割も果たしています。これまでに、ダウン症候群の一過性異常骨髄増殖症や、ダウン症候群の骨髄性白血病を対象とした臨床試験において、また、近年はランゲルハンス細胞組織球症においても、中央遺伝子変異解析を担当しています。また、JCCGの治療研究を計画し実施する立場からも、疾患委員、分子診断委員、中央診断委員を務めるなど、小児がんに対するより良い診断法・治療法の開発に取り組んでいます。
また、従来の治療法では治癒が困難であった難治性の血液疾患、小児がん、免疫不全症の患者さんに対して、積極的に造血細胞移植を行っています。当グループでは、1986年に第1例目の同種骨髄移植を行って以来、現在までに延べ200例以上の造血細胞移植を行ってきました。現在、年間4~10人の患者さんに対して移植を行っており、最近ではHLA半合致血縁者間移植などにも取り組んでいます。世界に先駆けた移植例としては、NEMO遺伝子異常による先天性免疫不全症の患者さんに対する世界初の同種造血幹細胞移植の成功例(Bone Marrow Transplantation, 2007)や、トリコスポロン感染症合併白血病患者さんに対してボリコナゾールを治療的・予防的に用いた臍帯血移植の成功例(Bone Marrow Transplantation, 2010)などが挙げられます。非血縁者間骨髄移植と臍帯血移植の施設認定を受けた県内唯一の小児科として、今後も移植医療に取り組んでいきたいと思います。
診療案内
1) 外来
水曜日 血液外来・造血幹細胞移植外来(午前)
青森県内を中心として、秋田県と岩手県の県北からも、毎週30人から50人程度の患者さんが受診しています。貧血、血小板減少症、凝固異常症などの血液疾患、小児がん、血管腫やリンパ管腫などの良性腫瘍、免疫不全症など、幅広く診療を行っています。また、日本造血細胞移植学会の研修を受けた専任の看護師が、医師と協力して、移植後の様々な合併症や問題に対応しています。
2) 入院
小児科病棟に、常時15~20人程度の患者さんが入院しています。グループカンファレンスを週3回、小児科全体の患者カンファレンスを週1回行っており、患者さんの診断・治療方針などについて活発に議論しています。また、月1回、小児外科・放射線科・患者さんの治療に関連する診療科と合同でカンファレンスを行い、各診療科が連携したより良い集学的治療を提供できるよう努めています。2015年3月からは病院全体のキャンサーボードの一部として、小児がんボードが開催されるようになりました。
造血幹細胞移植は、中央診療棟のICTU(強力化学療法室)で行っています。常時2~3人の患者さんが入室しており、年間4~10件の移植を行っています。患者さんの移植前には、医師と看護師による患者カンファレンスを行い、患者さんごとの問題点や移植スケジュールなどについて確認を行っています。稀な疾患に対する移植や合併症のリスクが高い移植を行う際には、国内の各分野の専門家と連携して移植を行っています。
研究
臨床においては最善の医療を提供することを目指して診療に励んでいます。しかし、その努力にも関わらず、残念ながら白血病等の難病を抱える子どもたちがすべて健康を取り戻せるわけではありません。治療成績をさらに向上させるためには、基礎研究が不可欠です。私たちは、特に、ダウン症候群の白血病とダイヤモンド・ブラックファン貧血(DBA)という遺伝性貧血に焦点を絞って取り組んでいます。この二つの疾患については、日本で発生するほとんど全ての新規症例の検体が、全国から弘前大学に集まってきます。
白血病は、多段階の遺伝子異常が蓄積して発症することが知られています。ダウン症児では、新生児期に5~10%が一過性異常骨髄増殖症(TAM)を発症し、その約20%が生後4年以内に真の白血病である急性巨核球性白血病(DS-AMKL)を発症します。このため、ダウン症は、前白血病から真の白血病へ進展する過程を経時的に観察できるたいへん重要な疾患であると考えられます。これまでに私たちは、赤血球・巨核球造血に重要な転写因子GATA1の遺伝子構造を明らかにし(Nature, 1993)、その遺伝子変異がほとんど全てのTAMとDS-AMKLに生じていることを見出しました(Blood, 2003)。ダウン症の一卵性双胎の研究により、出生前にGATA1遺伝子に変異が起こり、TAMが生じていることを見出しました(Blood, 2004)。また、TAMから白血病への進行に関わるリスク因子を発見し(Blood, 2010)、巨核球の異常増殖を抑制するGATA1の最小領域を同定しました(Blood, 2013)。さらに、最近、私たちはGATA1変異を持つTAM細胞にコヒーシン複合体/CTCF、EZH2などのエピゲノム制御因子、およびシグナル伝達系分子をコードする遺伝子群に高頻度の変異が生じていることを発見し、ダウン症の白血病に起こっている遺伝子異常の全貌を明らかにすることに成功しました(Nature Genetics, 2013)。今後も、小児白血病の画期的な治療法やさらに予防法を開発するために、貢献していきたいと考えています。
また、私たちはダイヤモンド・ブラックファン貧血(DBA)という先天性貧血の発症機序に関する研究も進めています。DBAの多くは、リボゾームというタンパク質の生合成を担っている細胞内器官に異常がみられます。私たちは日本全体におけるリボゾームタンパク(RP)遺伝子の頻度を初めて明らかにしました(Haematologica, 2010)。さらに、通常のシーケンスでは同定出来ないRP遺伝子の大欠失が約10%も存在することを見出しました(Blood, 2012)。これまでに次世代シークエンサーを用いた網羅的解析により、多くの新規原因候補遺伝子を見出し、機能解析が終了した原因遺伝子について最初の報告を行いました(Br J Haematol, 2015)。この分野でも、血液学の進歩に貢献し、診断や治療法の開発に繋がる発見が期待できます。
小児血液、小児がん、原発性免疫不全などの領域は稀少疾患が多く、「特殊から普遍へ」という考えを大切にしています。大きく考えながら小さく的を絞って研究することが、良い研究をするためには必要です。私たちの最終的な目標は、ダウン症の白血病やDBAの研究から小児白血病の発症や造血のしくみを理解し、小児の血液疾患の発症を予防することです。
血液グループのメンバー
照井 君典 (教授)
遠野千佳子 (医学部保健学科教授)
工藤 耕 (准教授)
佐藤 知彦 (助教)
小林 明恵 (助教)
田中 龍彦 (病院助手)
小原 玲音 (病院助手)
<研究>
土岐 力 (講師)
金崎 里香 (助教)
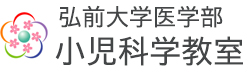
 教室紹介
教室紹介
 一般の方へ
一般の方へ
 学生・研修医の方へ
学生・研修医の方へ
 会員専用
会員専用